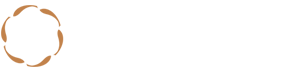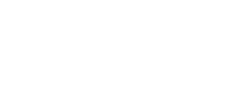錦絵の風景と鮎
錦絵と鮎
浮世絵とは、江戸時代中期から明治初期にかけて発展した木版画である。18世紀中葉から多色刷りの技術が発展し、「錦絵」が登場する。その主題は文字通り「浮世の絵」、「現世(うきよ)」の風俗を描いたものである。浮世絵は日本の芸術としてだけでなく、社会風俗の記録としても研究の対象となっている。
錦絵に「鮎」が描かれることがある。鮎は、日本の川魚の中でも特に風流な存在とされ、夏の到来を告げる季語でもある。透明感のある細身の姿、清流に棲み1年で命を終える儚いその生態は日本人のこころを揺さぶるのだろう。
鮎と多摩川
葛飾北斎が花・鳥・魚・小動物・器物を描いた10の図を収載した『肉筆画帖』に「鮎と紅葉」がある。水面の輝きと川底への深さに引きずり込まれる。歌川国芳の「萩に鮎」は水の揺らぐ表現が面白い作品だ。初代歌川広重「魚づくし鮎」は海外でも人気が高い。「秋の雨 ふりても水の かけきよく さひはみえさる 玉川の鮎」(春園静枝)の狂歌が添えられている。狂歌の挿絵として描かれているのかもしれないが、ともに味わうのがいいだろう。
広重には「名所雪月花 多摩川秋の月 あゆ漁の図」という作品もある。竿釣り、投網、四つ手網などと自然が交わる情景が叙情豊かに描き出されている。余談だが、多摩川の鮎は幕府への献上品になるほどで、代価を受け鮎を献上することを「上ヶ鮎御用(あげあゆごよう)」といったそうだ。
鮎が描かれた錦絵を掲載できないのは残念でならない(ウェブで画像検索を)。
多摩川と琵琶湖
東京都青梅市大柳町の青梅大柳河原に「若鮎の碑」がある。建設の由来として「大正二年六月(一九一三)東京帝国大学教授石川千代松博士はこの地先に琵琶湖小鮎数百尾を移植し遡上鮎のように大型鮎となるかの画期的実験を試みそれに成功し現在のように全国河川に琵琶湖産稚鮎の放流をみるに至りました 博士の功績をたゝえると共に日本最初の放流地奥多摩川大柳河原を記念するため(後略)」と刻まれている。
琵琶湖は、日本最大の淡水湖であり、特異な生態系をもつ水域である。一生湖にとどまり、河川を遡上しない鮎が「小鮎」で成魚でも10センチ未満と大きくならない。石川博士は、初夏、稚魚の成長が始まるタイミングで放流実験を実施したのだ。
今日、鮎の放流事業は全国的に行われているが、その原点に琵琶湖と多摩川を結ぶ実験があることを、改めて記憶にとどめる必要があるような気がする。博士のまなざしには、単なる魚の数の増減ではなく、自然と人間社会の共生の構図があったのではないだろうか。
あゆの店きむらでは、琵琶湖産の稚鮎を鈴鹿山系の伏流水で養殖し、鱗のキメが細かく、皮や骨がやわらかい大鮎に育てている。鮎は、かつて錦絵に描かれたように季節を告げる風物詩であった。養殖は今なお人と自然との対話を映す物語である。あゆの店きむらの塩焼きは、今年の夏の一編でしかない。対話の片鱗をぜひ、ご賞味あれ……。