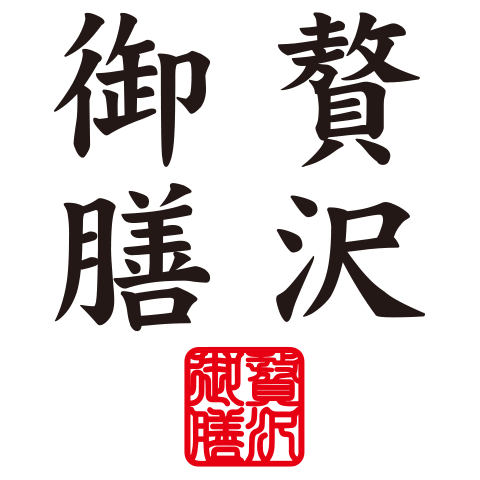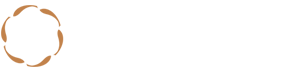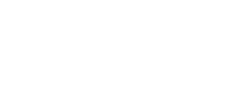近江千年、湖と山・川、大地の恵み
鮎は秋に川の下流で産卵し、稚魚は海へと下り、翌春ふたたび川を遡上して成長することはよく知られている。清らかな流れを好み、「清流の女王」と呼ばれるほど美しい姿をしている。川底の石に生える珪藻を食んで育つことから、その身には爽やかな香りが宿る。
鮎は山と海を結ぶ川を往還し育まれる自然の恵みである。
朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに
あらはれわたる 瀬々の網代木権中納言定頼『百人一首』
「網代木(あじろぎ)」は、川を下る氷魚(鮎の稚魚)を捕らえる仕掛けのことだ。宇治川は古来、氷魚漁や鵜飼で名高く都の食文化を支え、貴族たちは風雅を愛でることを惜しまなかった。鮎は単なる川魚ではなく、和歌に詠まれ、宮中に献上される特別な存在でもあったのだ。
ところが、琵琶湖の鮎は少し事情が異なり、湖と近江の山・川を往還して生きている。さらに川を遡ることなく一生を湖で過ごす鮎もいる。この鮎は成魚でも10センチ程度にしか成長せず「小鮎」という。こうした独自の生態は、琵琶湖という特異な環境がもたらしたものだ。鮎は近江の山・川、湖をつなぐ循環そのものを象徴する魚でもある。
「あゆの店きむら」は、鈴鹿山系の伏流水を地下100メートルから汲み上げて、琵琶湖産の鮎を養殖している。養殖池には川の上流のような速い流れを作り出し、余分な脂を落とすことで、身が締まり天然に近い味わいの鮎が育つ。さらに、餌にも工夫を凝らして、一般的な養殖鮎に比べ脂肪分を半分ほどに抑え、上品で淡泊な鮎に仕上げている。そして、高品質な仕上がりにするために、鮎が成魚になる段階で、餌の配合を変更している。例えば、ラン藻類の一種であるスピルリナやプロポリスを与えることで健康な鮎を育て、天然鮎に負けない香りや食味を実現した。
鮎のなれ寿し
近江に伝わる「なれずし」は日本の最古の寿しといわれている。漢字で「なれ」は「熟れ」と書く。その代表が「鮒寿し」だ。
奈良時代にはすでに製法が確立していたという。琵琶湖畔に鮒寿しが誕生した要因は、湖にニゴロブナが生息していたこと、旨い米が穫れたこと、淡水を容易に使える水環境があったこと、発酵に適した風土であったこと、そして、塩が豊富に手に入ったことである。
そして、この発酵の知恵は単に保存のためだけでなく、独特の酸味と旨みを生み出す味覚として洗練され、湖魚を用いたさまざまな「なれずし」の食文化を育んできた。「鮎のなれ寿し」もそのひとつだ。
「あゆの店きむら」では、長年培ってきた鮒寿しの製法を応用し、鮎のなれ寿しを漬け込んでいる。発酵する期間をほどよく抑えることで、近江米のまろやかさが融合し、独特の酸味と淡泊な旨味が立ち上がる……。
鮒寿しとはまた異なる琵琶湖千年の風味である。
大袈裟にいえば、そのひと口は、湖、山・川、大地……近江という風土を丸ごと味わう体験にほかならない。